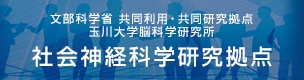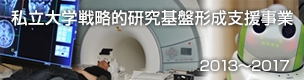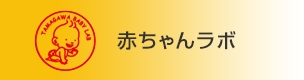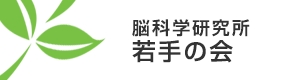被虐待経験がある児童は他者の幸せな表情を理解するのが苦手-米国科学雑誌に論文を発表-
玉川大学脳科学研究所(町田市玉川学園6-1-1 所長代行:坂上 雅道)の高岸 治人(たかぎし はると)助教と北海道大学の小泉 径子(こいずみ みちこ)大学院生・ 日本学術振興会特別研究員らは、被虐待経験がある児童は他者の幸せな表情を理解するのが苦手であることを実験によって明らかにした。本研究成果は、米国の科学雑誌“PLOS ONE”(オンライン版)に2014年1月20日(米国東部標準時間)に掲載される。
【掲載論文名】
The Relationship between Child Maltreatment and Emotion Recognition(児童虐待と感情理解の関係)http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0086093
【著 者】
高岸治人(玉川大学脳科学研究所)*研究グループ責任者
小泉径子(北海道大学)
児童虐待の報告件数は年々増加の一途をたどっており、児童虐待の防止や対策、そして被虐待経験が児童のこころに与える影響を明らかにすることは我が国にとって急務であることは間違いありません。本研究では、被虐待経験がある児童と被虐待経験がない児童を対象に他者の表情からその人物の気持ちを推測させる課題を行うことで、被虐待経験と他者の表情理解の関連を検討しました。
研究の結果、被虐待経験がある児童は、他者の幸せそうな表情や優しい気持ちの表情といったポジティブな感情に関する表情理解が苦手であることが明らかになりました。私たちは、自身が感じている気持ちを手がかりにして他者の気持ちを推測することが分かっていますが、被虐待経験がある児童が他者のポジティブ感情に関する表情理解が苦手であるという本研究の結果は、被虐待経験がある児童がポジティブな感情をこれまで経験することが少なかったことが原因の一つであると考えられます。被虐待経験がある児童が示すこころの特徴を明らかにすることは、児童が保護された後の社会適応へのケアに貢献すると期待されます。
資料
実験方法
被虐待経験がある44名の児童(被虐待経験ありグループ)と、被虐待経験がない85名の児童(被虐待経験なしグループ)を対象に、人物の目の周辺が写った写真を見て、その人物が感じている気持ちを推測し回答してもらう課題を行いました(図1)。写真は合計28枚あり、4つの選択肢の中から一つを選ぶという方式で行いました。課題はそれぞれポジティブ感情に関する表情(例:幸せな気持ちでいる、優しい気持ちでいる等)が7枚、ネガティブ感情に関する表情(例:悲しんでいる、うろたえている等)が10枚、ニュートラルな表情(例:考え事をしている等)が11枚で構成されていました。
実験結果
被虐待経験ありグループ、および被虐待経験なしグループの正答率を比較した結果、ネガティブ感情とニュートラルに関する表情では、2つのグループの間の正答率に差は見られませんでしたが、ポジティブ感情に関する表情においては、被虐待経験なしグループ(56%)よりも被虐待経験ありグループ(45%)の方が低いという結果が得られました(図2)。
実験の成果
この結果は、被虐待経験のある児童は、他者のポジティブ感情に関する表情理解が苦手であるということを示しています。被虐待経験のある児童は、保護された後の社会適応が難しいことが知られていますが、本研究の結果で得られた、他者のポジティブな表情理解が苦手であるという特徴は、社会適応の困難さの原因の一つとして考えられます。今後は、被虐待経験と表情理解の間の因果関係や、保護された後に、ポジティブ表情の理解が回復するのかどうかを明らかにすることが期待されます。
<図1> 研究で用いた課題

参加者は写真を見て、その人物が感じている気持ちを推測した。写真の周りに4つの選択肢(感情を表す言葉など)があり、参加者はそのいずれか一つを選択した。
※上で用いた写真は、プレスリリース用に、実験で用いた写真に似せて新しく撮影した。
<図2> 被虐待経験がある児童の表情理解に関する特徴

被虐待経験がある児童は、被虐待経験のない児童に比べて、ポジティブ感情(例:幸せな気持ちでいる、優しい気持ちでいる等)に関する表情の正答率が低いことが明らかになった。ネガティブ感情(例:悲しんでいる、うろたえている等)に関する表情、ニュートラル表情(例:考え事をしている等)においては正答率に差はみられなかった。(*は、統計的に差が見られた箇所(1%水準))。